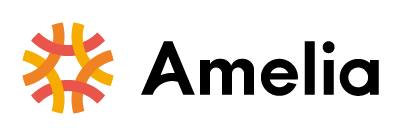大井 祐子さん
カレッジコースで充実の学び
プロフィール
幼少期を東南アジアで過ごし、社会をより良くする仕組みづくりに関心を持つ。大学卒業後、外資系IT企業や政策実施機関等にて、主にサービス・小売業向けシステム開発プロジェクトや産学官連携事業に従事。業務の一環で翻訳や海外機関とのやりとりに携わり、「わかりやすく、読み手に正しく伝わる文章」の重要性を実感する。地方への転居と子どもの小学校入学を機に、翻訳を基礎から学び直すため、フェロー・アカデミーのカレッジコースに入学。これまで関わってきた先端テクノロジーや日英の翻訳に引き続き携わることができるよう、日々研鑽を積んでいる。趣味は鉛筆画、スノーボード、読書(特にノンフィクション、スポーツ漫画)。富士登山にも挑戦してみたい。
外資系IT企業から政策実施機関を経て地方都市へ
加賀山 :本日は、静岡県でフェロー・アカデミーのオンライン講座を受けておられる、大井祐子(おおい ゆうこ)さんにお話をうかがいます。いまカレッジコースを受講されていて、その学習内容を中心に聞かせていただければと思います。カレッジコースで学ぶのは4月から翌年3月までの1年間ですか?
大井 :はい。今年3月の第2週に修了式があります。学校の教室と、オンラインのハイブリッド形式で送り出していただくそうです。
加賀山 :カレッジコースに入るまえの職歴について、可能な範囲で教えていただけますか?

家族旅行は人生の楽しみのひとつです。今年はマレーシアに行ってきました。
大井 :もともと開発途上国(マレーシアとシンガポール)で育ち、社会をよりよくする仕組み作りのようなものに関心がありました。大学生活を過ごした2000年代前半~半ばは、ちょうどITがインフラとして広く社会へ浸透していった時期で、そこに可能性を感じて、最初のキャリアを外資系IT企業で始めました。10年間在籍したあと、政策実施機関に勤めました。
加賀山 :かよった大学は日本でしたか?
大井 :そうです。マレーシアとシンガポールで暮らしたのは、小学校の途中から中学校の終わりまでです。
加賀山 :すると、英語に加えて中国語もできるとか?
大井 :それが日本人学校だったんです。語学力の習得という観点では、現地校やインターナショナルスクールに行ったほうがよかったですよね(笑)。ただ、日本人学校の生活もすごく楽しかったです。マレーシアにはいろんな民族・宗教・文化の方々が暮らしていて、みんな違うのが当たり前という環境で、いい影響をたくさん受けました。人とのコミュニケーションにおいて、相手の背景や考え方を尊重することや、その人のよい面にフォーカスするとことの大切さはマレーシアの文化から学びました。
その後、京都にある高校と大学に通い、社会人になってからは、16年間東京で暮らしました。最初に勤めたIT企業では主に営業職として、お客様の企業課題や業務課題をお聞きしてITでどう解決するかをチームで提案していく仕事に従事しました。
加賀山 :ソリューションビジネス的な? かなり理系の知識も必要になると思いますが、勉強されたのですか?
大井 :ΙΤについては、入社後に学びました。高校生のときは理系教科におもしろさを感じていましたが、大学の学部を選択する際、社会を変える仕組み作りというと法律や教育、国際協力という思いがあり、文系に進学しました。
ただ、大学生になってみると、それらが社会を変える仕組みとしてとても重要であると改めて知る一方で、歴史が長く、関係者も多く、変化には丁寧なプロセスとおおくの時間を必要とする業界なのかなあとも感じました。それに対してITは、まっさらな状態に仕組みを導入することで一気に物事を変えていくポテンシャルがすごいなと思ったんです。
加賀山 :なるほど。そのあと勤められた政策実施機関というのは、どういうところですか?
大井 :文部科学省所管の国立研究開発法人のひとつで、科学技術・イノベーション政策を支援・推進することを目的とした機関です。産学官で連携して研究開発拠点の構築を支援する事業などにたずさわりました。
たいへんやりがいのある仕事でしたが、家族の都合で静岡県に引っ越すことになり、退職しました。
自宅でカレッジコースを受講
加賀山 :地元でしばらく勤められて、その次がフェロー・アカデミーのカレッジコースでしょうか?
大井 :そうです。静岡でお仕事のご縁をいただいたものの、今後もまた転居がありそうだということになり、居住地や勤務地に縛られない働き方を模索しようと思いました。小学生の子どもがふたりいるんですが、下の子が小学校に上がるタイミングで、カレッジコースに入学しました。
加賀山 :それが大きな動機だったのですね?
大井 :そうなんです。上の子が小学校に上がったときに、保育園と小学校はだいぶ違うなと感じました。保育園では、いつも先生方が手厚く見守ってくださりましたが、小学校では、教育の場として、「自分のことは自分でやる、できないことは家庭でフォローする」ことが基本になり、夫婦ともに家をあけることが多かった我が家の場合、子どもの負担が増えてしまいました。そこで、子どもがふたりとも小学生になるタイミングで、自宅で働くことができるスキルを身につけようと決心しました。
加賀山 :そういう仕事を探したときに翻訳が頭に浮かんだのはなぜですか? 昔から好きだったとか?
大井 :翻訳を選んだ理由はふたつあります。ひとつは、これまで、国内外の産学官関係者の方々といっしょにプロジェクトなどに従事してきた経験から、関係者のコンセンサスを得るには、「わかりやすく、読み手に正しく伝わる文章や資料」がとても重要であることを実感してきたためです。
とくに海外の方々とやりとりするうえでは、お互いの常識も違い、スピード感や文化も異なるなかで、認識のすり合わせにおいて、文字に起こされた文書がすべてというところがありますよね。業務の一環として、翻訳に取り組む機会もいただいてきましたが、「この翻訳で、文書作成者の意図を正しく読み手に伝えられただろうか」と力不足を痛感することが多く、原文の内容をきちんと読み手に伝えることができる人になりたくて、翻訳の道をめざすことに決めました。
やるならまず1年間みっちり勉強したい、現役のプロの先生方に基礎からしっかり教わりたい、分野別の翻訳や業界情報なども総合的に学んでみたいと考え、カレッジコースに入学しました。
加賀山 :なるほど。もうひとつは何でしょう?
大井 :やはり好きなことに挑戦してみようという気持ちです。好きなことに没頭する子どもたちを見ていると、キャリアを変えるこのタイミングで、自分も挑戦してみようと思いました。
昔から語学を学ぶことが好きで、とくに、コミュニケーション手段としての側面に関心がありました。「同じ単語でも、場面によって訳出が変わるのはなぜだろう」、「文末表現を少し変えると、なぜ相手の受け取り方が違うのだろう」といったことを、文法解釈などで紐解いていくことが楽しいです。
実際、営業職や事業推進職の現場でも「お客様にAと伝えるといまひとつの印象を与えてしまったのに、A+αと伝えるといい印象を持ってもらえた」ということが少なからずあって、物事を前進させるために、言葉の選び方がいかに重要であるかを感じながら働いていました。引き続き、原著者の伝えたいことを読み手にどれだけわかりやすく伝えられるかということを意識して、翻訳に挑戦していきたいです。
加賀山 :アメリアにはいつ入られましたか?
大井 :2022年秋に、フェロー・アカデミーの通信講座(実務翻訳<ベータ>)を受講するタイミングで、アメリアに入会しました。
加賀山 :アメリアは日頃どんなことに役立っていますか?
大井 :コラム欄の「ミニ英訳ドリル」、「日本語にしにくい英語」から会員の方々の訳を学んだり、「アメリア会員インタビュー」、「ご利用企業インタビュー」の記事から仕事獲得に向けて自分がやるべきことをリストアップしてみたり、求人検索から翻訳業界の動向を確認したりしています。コース修了後は、定例トライアルにも応募していきたいです。
カレッジコースと日々の生活
加賀山 :カレッジコースの授業についてうかがいます。恥ずかしながらよく知らなかったのですが、4月から翌年3月まで、本格的な大学のように毎週平日の朝から夕方まで授業があるんですね。このなかのどれを受講されましたか?
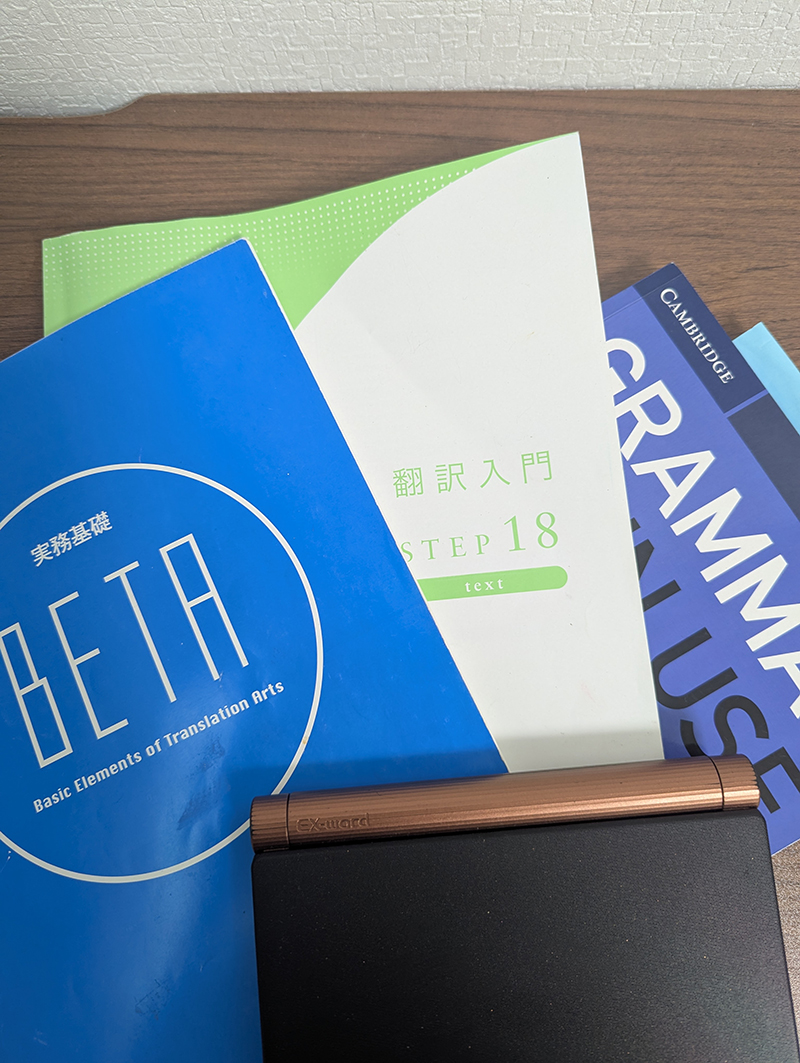
カレッジコースで受講した教材は、修了後も復習に活用しています。
大井 :まさに大学のように前期と後期に分かれていまして、前期は必修科目である「出版」、「実務」、「映像」の基礎講座3つと「翻訳入門」、選択科目である「総合英語」を受講しました。前・後期をつうじて、必修科目の「日英翻訳」と選択科目の「TOEICトレーニング」も受講しました。
後期からは選択科目として、「IT・マーケティング」、「メディカル」、「ビジネス法務」、「ドキュメンタリー」、「出版総合」を取りました。
加賀山 :いまおっしゃられたのを全部合わせると、1年間ほぼ毎日(平日)夕方まで埋まりますよね。
大井 :そうですね。予習・復習、宿題とあわせて、本当に学生以来の勉強量でした(笑)。
加賀山 :大学よりも授業が多い気がします(笑)。
大井 :キャリアのスタートがITでしたから、翻訳でもIT分野を中心に勉強しています。もうひとつは自分にとって新しい分野なんですが、金融・経済関係の日英の翻訳・校正をできるようになりたいと思っています。
加賀山 :ほう。金融・経済関係の翻訳の需要があるということですか?
大井 :2025年4月から「プライム市場上場企業に対する日本語と同時の英文開示の義務化」が決まっていることを受けて、当面、この分野で日英翻訳の需要が増えそうだというお話を伺いました。お客様企業と海外関係者のコミュニケーション促進に資する業務である点に魅力を感じています。
加賀山 :ChatGPTなどのAIも活用されますか?
大井 :コースの課題に取り組む際、主に調べものに活用しています。自分で課題訳文を作ったあと、「この解釈で合っているか」と質問し、そこで得たキーワードをヒントにして参考書を確認するというかたちで、学習にも使っています。
加賀山 :やはり金融翻訳をしておられる方が、AIは英日よりも日英翻訳に使える、英語の訳文をどんどんブラッシュアップしていける、とおっしゃっていて、なるほどと思いました。私自身は出版翻訳だけなので、AIを翻訳そのものには使っていないのですが、とくに実務翻訳ではなんらかのかたちでAIを使うことがますます増えるでしょうね。
大井 :講座の先生方も、「AIを活用する際には、自分の軸を持ちましょう」ということをおっしゃいますね。ただAIのアウトプットを鵜呑みにしたり、「なぜこんなふうに訳出されているのか」と考えなくなったりしたら終わりだから、自分の軸を持ってAIとうまくつき合う方法を考えましょうと。
加賀山 :AIは嘘がすごく得意ですからね(笑)。まわりの文脈を見事に整えてくるから、嘘をつかれてもなかなかわかりません。
大井 :すごくうまく何かが抜けていたりしますよね(笑)。
加賀山 :子育てとの両立はどのようにされているのでしょう。たとえば「ビジネス法務」は午後5時15分までありますよね。そのときなど、お子さんはどうされているのですか?
大井 :私は自室でオンライン授業中であることが多いので、子どもたちが帰ってきたときようにリビングにお菓子をたくさん出しておいたり、授業の合間に、子どもと一緒に翌日の学校の準備をしたりしています。
加賀山 :お母さんが家にいることを、お子さんはやはり喜んでいますか?
大井 :そうですね。安心するようです。上の子は、わりとたくましくなんでもできる感じに育ってくれていますが、私が日中家にいることで、ちょこちょこ「今日学校でこんなことがあってさ」と話してくれるようになりました。会話がすごく増えました。
加賀山 :きっとこれまでも話したかったんでしょうね。
大井 :そうなんだろうと思います。やっぱり思いきって家にいる生活に挑戦してみてよかったと思います。
目標めざして学友と切磋琢磨
加賀山 :今後の話ですが、出版翻訳とか映像翻訳は考えておられませんか?
大井 :当面は実務翻訳者をめざしていきたいと思っています。ゆくゆくは、それに関連する動画の字幕や、冊子の翻訳なども手がけられるよう、研鑽を積んでいきたいです。
加賀山 :カレッジコース修了後の就職活動はどうされますか? カレッジコースで就職の相談のようなこともできると聞いていますが。
大井 :相談できます。まず、フェロー・アカデミーと翻訳会社の方々が、授業とは別枠で企業説明会を実施してくれます。その場で、翻訳会社の方々から、企業概要や業務内容、求人情報、選考の流れについて直接お話を聞くこともできます。ほかにも、フェロー・アカデミー事務局の方々が希望者向けに模擬面接会を実施してくれたり、適宜個別相談にのってくれたりと、幅広いサポートを受けることができます。
私は金融関係の日英翻訳にかかわるお仕事をめざしています。それと並行してIT分野の勉強も続けながら、ITと金融分野の実務翻訳者をめざしていきたいと思います。
加賀山 :大学よりも授業は多いし、大学よりも丁寧に就職の世話もする印象ですね。宣伝になってしまいますが(笑)。
大井 :すごくいいコースだと思います。私は社会人経験者ですが、大卒でそのままこのコースに入学する方も多く、とくにそういう方々にとっては、就職サポートや面接の受け方にもアドバイスがもらえる点、心強いのではないでしょうか。私も新卒で就職活動をするときに、こんなサポートを受けたかったなと思います(笑)。
加賀山 :それ書いときます(笑)。
大井 :先生方も魅力的で、翻訳の授業はもちろん、雑談も含めてとにかくお話がおもしろいんです。受講生は、世代もバックグラウンドもそれぞれ違うけれど、みなさん翻訳や語学が好きな方々で、一緒に学びながら、よい刺激をたくさんもらっています。

毎年冬はスノーボードへ。子どもの上達スピードには目を見張るものがあります。
加賀山 :受講生同士の交流もあるのでしょうか?
大井 :イベントとして、入学式、修了式があります。通学している人たちは毎日学校で会って仲よくなるそうです。オンラインでも授業のグループワークなどをつうじて、自然と関係づくりができると思いました。
加賀山 :グループワークというのは、翻訳について話し合うということですか?
大井 :はい。たとえばメディカルの授業では、受講生が提出した翻訳課題から先生が選択したものを、受講生たちでチェックし合い、最後に先生が講評してくださるというグループワークがありました。
加賀山 :目的が絞られているから、みんなの意識が共通していますよね。
大井 :そう思います。ですから雰囲気もよくて、気軽に質問したり、情報交換しやすく感じます。事務局の方々がしっかりサポートしてくれるのでオンラインの人も安心して受講できると思います。授業は全部ハイブリッド形式で、オンライン受講者が困らないように、ファイルの共有とか、画面の映り方とか、すごく配慮されていて。
加賀山 :受講生は何人ぐらいでしたか?
大井 :今年は約20人でした。科目にもよりますが、そのうち3分の1から半分くらいの方がオンラインで受講しています。ふだんは通学の方も、科目によってはオンラインで参加している方もいます。たとえば、1日3コマ入っているときには学校で、1日1コマのときは家から受けるといったふうに使い分けている人も。映像翻訳の授業では、先生が字幕制作ソフトのBabelを画面共有しながら説明してくれます。
加賀山 :よくできていますね。ほかに将来的に考えておられることはありますか?
大井 :チェッカー、ポストエディター(機械翻訳の訳文を修正する)の力もつけなければなと感じています。企業の中には、AIや機械翻訳を、ビジネスを進めるうえでのチャンスととらえている方々も多いと思います。そういうニーズにも応えられるように、AIや機械翻訳とうまく付き合いながら、スピード感を持って応対できる力をつけたいです。ただ、ポストエディットの訳文を見て、どこが合っていてどこが間違っているかわかるには、一から翻訳できる力がないといけませんから、結局、自分で翻訳できる力が何より大事なんだろうなと思います。
■ きちんと計画を立てて、やるべきことを着実にやっていく方とお見受けしました。このインタビューの予習(?)として、私の訳書を読んでくださったことからもそれはうかがえます(ありがとうございました)。めざす企業に入って、ぜひ活躍されますように!